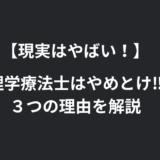※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。
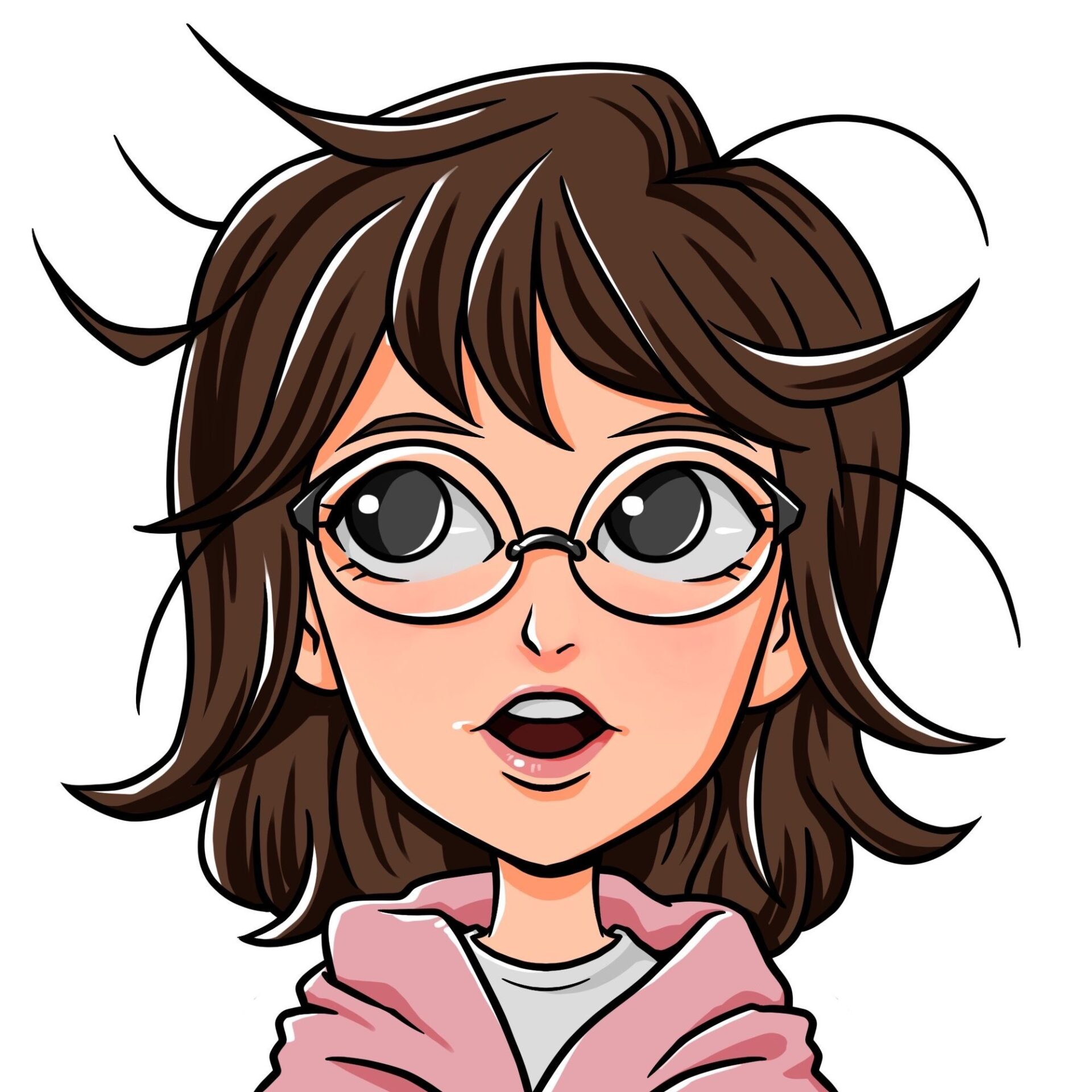
副業に興味があって、他の療法士の人がどれくらい副業をしているのか気になります…
周りに副業の話ができなくて、どれくらいの人が副業をしているのかを知りたいです..
今回の記事を読むと「療法士がどれくらい副業をしているか?」についての疑問が一つ解決できます。
副業・兼業に関する厚生労働省の調査と今回独自の調査も行ったので調査結果も交えて紹介します。
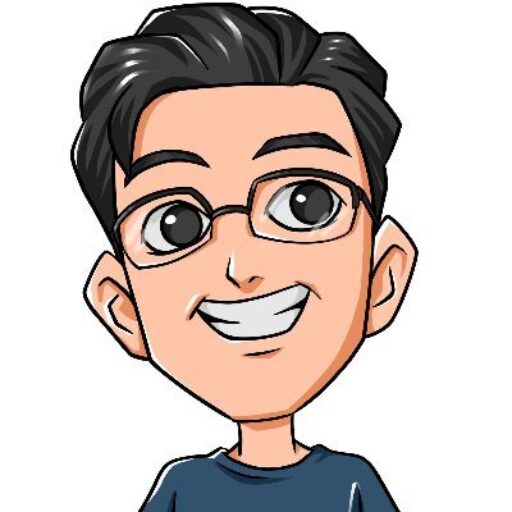
理学療法士です。
副業歴10年の経験があります。
目次(クリックすると自動で飛びます)
結論
「医療・福祉関係者が副業をしている割合は9.9%」
一方で、独自調査した結果「療法士の約90%が副業をしている⁉」という事実が判明しました。
※療法士の副業をしている割合については調査にバイアス(偏り)がかかっている可能性が十分にあるので注意は必要です。
厚生労働省による調査より
厚生労働省が第132回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)で副業に関する資料を出しています。
厚生労働省が調査会社に委託してインターネット調査が行われました。
方法は以下の通りです。
〇調査期間
出典:厚生労働省
令和2年7月23日~令和2年7月29日
〇有効回答数
・調査会社が約67万人に調査回答依頼のメールを送信、約23万人から回答を得た。
副業をしている割合
・「副業をしている割合」は全体で9.7%
・副業をしている人の本業の形態で一番多いのは「フリーランスの人」で29.8%
・副業をしている人の本業の形態で一番少ないのは「正社員」の人で5.9%

副業をしている業態
厚生労働省の調査では、副業をしている中で9.9%の人が「医療・福祉」分野で働いていることが分かっています。
ちなみに、厚生労働省の調査は「医療」と「福祉」の分野の人たちが混ざっています。
さらに、「療法士」に特化したアンケートはされていません。

副業をしている理由
厚生労働省の調査では、副業をしている理由は「収入を増やしたいから」が56.5%と最も高い結果でした。
続いて、「1つの仕事だけでは収入が少なすぎて、生活自体ができないから」が2番目に高い結果となっています。
副業をしている理由は、「経済的理由(収入増加が目的)」のようです。

独自調査の内容
「療法士が副業をどのくらいしているのか?」について独自調査をしました。
クラウドソーシングを利用し理学療法士、作業療法士、言語聴覚士にアンケート調査を行いました。
〇調査期間
令和5年3月7日~3月10日
〇調査人数
療法士(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)87人から回答を得た。
Q1.現在、副業をしているか?
Q2.副業をしている理由は何か?
Q2に関しては複数回答可としました。
Q2の回答内容は以下の通りです。
- 収入を増やしたいから
- 自分が活躍できる場所を増やしたいから
- 人脈を増やしたいから
- スキルアップしたいから
- 地域・社会貢献のため
- その他
独自調査の結果
療法士が副業をしている割合
療法士が副業をしている割合は「87.8%」でした。

療法士が副業をしている理由
副業をしている理由として、1番多かった回答が「収入を増やしたいから」、2番目が「スキルアップしたい」、3番目が自分の活躍できる場所を増やしたい」でした。

2つの調査結果から
厚生労働省の調査では療法士がどのくらい副業をしているかについてはアンケートがされていません。
療法士に特定されていませんが「医療・福祉」分野で働いている人が副業をしている割合は全体の9.9%という結果でした。
独自の調査結果では「療法士の人が副業をしている割合が87.8%」でした。
2つの調査結果を比較し、独自調査の結果は「副業をしている割合」が高く示され調査結果が大きく異なりました。
「副業をしている理由」に関しては、どちらの調査も「収入を増やしたい」が1番の理由でした。
副業をしている割合が高い要因
「副業をしている割合」が大きく異なった要因として「属性が違った」ことが考えられます。
2つの調査を受けた人たちの「属性が違った」
調査を受けた人たちの「属性」が違った
「属性が違う」とは、簡単に言うと考え方や世界観が全く違うという事です。
今回で言えば、「副業を既にしている人たちの属性」と「全く副業に興味がない人たちの属性」です。
独自の調査はクラウドソーシングを利用してアンケートを行いました。
クラウドソーシングはネット上で仕事を依頼したり仕事を受けたりする事ができます。
つまり、独自調査を受けた人のほとんどが既にネット上で何らかの仕事や副業をしている人たちであった可能性が考えられます。
独自調査を受けた人たちは偏りがあった可能性が十分にあるというわけです。
副業を始めるなら今がチャンス⁉

厚生労働省の結果から「医療・福祉」分野の人が副業をしている割合は10%未満と少ない結果でした。
私の肌感でも厚生労働省と同等だと感じています。
しかし、独自調査では療法士の人が副業をしている割合が高かったです。
理由は副業をしている人が多いところにアンケート調査をした可能性があるからだと先程述べました。
現実的には療法士はまだまだ副業をしている人は少ないけれど、副業をしている人は既に始めているいうことです。
副業をしている人が少ないということはまだまだチャンスがあるという事だと思います。
なぜチャンスがあるかというと競合(ライバル)が少ないからです。
一方で、既に副業を始めている人がいるという事に焦りを感じた方が丁度いいのではないかと思っています。
私は副業推進派です。
今の療法士を取り巻く社会情勢を考えると極端に言えば副業は必須だと考えています。
「副業をしていない人」について考えてみた
副業をするしないは自由ですが、私は副業をする方が断然いいと思っています。
一方で副業に興味すらない人も存在します。
副業に興味がない人のことについて考えてみました。
現状に満足している
副業をしている理由の1番は「収入を増やしたい」でした。
逆に副業をしていないとしたら今の待遇や給料に満足している可能性があります。
お金に困っていないという事です。
副業がバレるのが怖い
私の周りには、病院や施設に副業をしているのバレるのが怖くて副業をしない人もいます。
情報感度の違い
私は「副業に興味がない」と言う人は情報感度が低い印象があります。
例えば、社会情勢や現在の医療や介護保険状況について興味がないのです。
今後療法士が取り巻く状況や職業の将来についての危機感が薄いためアンテナが立っていないのではないかと考えています。
行動力の違い
私の同僚の療法士の話です。
同僚は口癖のように「給料が安い」と言っています。
「給料は安い」と言いますが、全く行動できてない人がほとんどです。
大抵の場合が給料を上げるような努力もしていないし、副業や転職をしようという行動もみられません。
副業はみんなが始めてから自分も始める⁉
周りの人と同じような行動を取ろうとする人がいます。
「みんなと同じ」という考え方です。
いつの間にか「みんなと同じ」という考えになっている事もあるので注意が必要です。
例えば、
・周りの人が新築のマイホームをフルローンで購入しているから私もフルローンで家を購入する。
・周りのみんなが結婚したから私もそろそろ結婚する。
などです。
自然と自分が気づかない内に周りの人と同じような行動を取っていることがあります。
副業の場合はどうでしょうか?
周りに副業をしている人がいないと、副業をしようという考えすら湧かない人もいるわけです。
「療法士がどれくら副業をしているか?」は気にしないで、自分にとって副業が必要だと判断したら直ぐにでも行動しましょう。
まとめ
今回「どれくらいの療法士が副業をしているのか?」について厚生労働省の調査と独自の調査結果を交えて解説してきました。
結果は以下の通りです。
厚生労働省の調査結果
・副業をしているのは全体の9.7%
・「医療・福祉」分野の人が副業をしている割合は9.9%
・副業をしている理由で一番高いのは「収入を増やしたいから」
出典:厚生労働省
・療法士が副業をしている割合は87.8%
・副業をしている理由第1位「収入を増やしたい」、第2位「スキルアップしたい」、第3位「自分が活躍できる場所を増やしたい」
副業をしている理由は、2つの調査結果は同様に「収入を増やしたい」でした。
一方で、副業をしている割合が大きく異なりました。
厚生労働省の調査結果では、療法士ではないにしても「医療・福祉」分野の人が全体の9.9%しか副業をしていないという結果でした。
独自の調査では療法士で副業をしている割合は87.8%と厚生労働省の調査結果に比べ高い結果となりました。
2つの調査で異なる結果となった要因として「属性が違う」ことが考えられます。
独自の調査ではクラウドソーシングで療法士にアンケート依頼を行いました。
クラウドソーシングはネット上で仕事を依頼や受注ができます。
つまり、今回の独自調査でアンケートに回答した人たちのほとんどがネット上で何らかの副業を既に始めていた可能性があります。
アンケートを回答した人たちはバイアス(偏り)がかかっていた可能性が十分に考えられます。
私の肌感としては厚生労働省の調査結果の方が現実的に合っていると思っています。
療法士の中で副業をしている人はまだ少ないかもしれませんが、副業をしている人は既にしているという事です。
副業をしている人が少ないという事は競合(ライバル)が少ないということでまだまだチャンスがあると思っています。
しかし、副業を既に始めている人もいることを理解し少々の焦りや危機感を持ってもいいのではないかとも思っています。
「みんなが副業をしてから副業始める」のではなく、社会情勢や自分の将来のことをよく考えた上でより良い選択と行動を取って欲しいものです。